鞍馬山~天狗の棲まう山に幼き義経を訪ねて~
- kk
- 2022年6月10日
- 読了時間: 4分
更新日:2022年6月27日
くらまやま
標高:584m
所在地:京都市左京区
コース:鞍馬寺→木の根道→貴船神社
コースタイム:約1時間

本日は鞍馬駅をスタート
天狗の面👺がお出迎え

鞍馬石
鞍馬石はほどよい錆が特徴
錆が「さび」に通じることから
日本の庭園作りに欠かせない石だとか
石に立ってパワーを感じるスポット

大天狗さま
鞍馬の旅に行ってきます♪

鞍馬寺到着
看板にはガイドマップが

鞍馬山案内
Guide Map of Mt.Kurama
入口でもらえる
①~㊶まで見どころ満載!

①仁王門(山門)
ここで拝観料を払う
上のガイドマップゲット♪
狛虎
鞍馬寺の御本尊の一である毘沙門天は
寅の年・寅の月・寅の日・寅の刻に出現
毘沙門天のお使いである虎は大切にされ
鞍馬寺では仁王門と本殿に狛虎が鎮座

⑥普明殿(ケーブル山門駅)
山門を入ってすぐケーブル乗り場が

牛若號Ⅳ
さっそく乗ってみた!

ケーブルカーを降りると
⑦多宝塔(ケーブル山上駅)
千手観世音・毘沙門天王・護法魔王尊
尊天三尊像を奉安

⑧新参道 をゆく

⑨弥勒堂
鞍馬寺はどこもかしこも朱が映える

㉔転法輪堂 と手水舎
紫陽花と竜がすてき
中にはとても大きな阿弥陀仏が

㉖本殿金堂
ここにも狛虎♪「あうんの虎」

いよいよ本殿裏の奥の院道へ

森の空気が気持ちいい

㉚與謝野晶子 歌碑
何となく 君にまたるる ここちして
いでし花野の 夕月夜かな

㉚與謝野鉄幹(寛)歌碑
遮那王が 背くらべ石を 山に見て
わが心なほ 明日を待つかな
遮那王は義経の稚児名
背くらべ石はこの先!楽しみ♪

㉜霊宝殿
ふらりと立ち寄った霊宝殿
「百の義経展」が開催されていた!
『鎌倉殿の13人』では菅田将暉が好演
母の常盤や鞍馬時代の牛若伝説
義経や弁慶の太刀の展示にも大興奮♪
国宝 毘沙門天三尊立像も素晴らし~

冬柏亭(とうはくてい)
與謝野晶子が50歳のお祝いに
弟子たちから贈られた書斎だとか

すごい木がたくさんある

㉝息つぎの水
牛若丸が毎夜奥の院へと
剣術の修行に通ったときに
この清水で喉を潤したという

㉞屏風坂の地蔵堂

㊱木の根道
とても静かで力を感じる場所
牛若丸兵法修行の場

㉟背比べ石
鞍馬山で修行を重ねた牛若丸が
奥州平泉の藤原氏の許に下るとき
鞍馬山を名残り惜しんで背比べをした石

㊲大杉権現社
2018年の台風21号により
大杉権現社は倒壊
倒れた大木が横たわっている

立派な杉が見えてきた
義経堂の案内板

㊴義経堂
義経の魂は鞍馬山に戻ったと信じられ
護法魔王尊の脇侍・遮那王尊として
ここに祀られている

義経堂の周辺は老杉が高くそびえる
老杉がが倒れて橋のように
神秘の世界への誘い

鞍馬山を越えて貴船へ
初めての川床料理

鮎の塩焼きにあまごの天麩羅
あぁ美味しいなぁ

岩の上にカワトンボ

川の流れの音をずっと聴いていたい
そんなひとときに感謝

お世話になった貴船茶屋
ぜひまた来たい

鞍馬・貴船はユキノシタの季節

貴船神社
水の神様を祀る神社
牛若丸も平家討伐を祈願したとか
平安時代に和泉式部が夫との復縁祈願
見事に成就したことから縁結びの宮に

鳥居をくぐってすぐのところに
苔むした大きな木

参道の赤い灯籠がきれい

㊶西門
再び鞍馬山越えで鞍馬駅を目指す
当日なら拝観券があれば再び入山可能
時間が遅いのか門のおじさんがいない…

帰りの登山道
行きには気づかなかった石のほこらや

天狗岩を見つけたり
(行きはお腹がすいてたのかな?)

㊵奥の院魔王殿
人影もなくひっそり

㊳僧正ガ谷不動堂
天狗👺と牛若丸が出会った場所

本殿と狛虎まで戻ってきた
誰もいない!

㉓巽の弁財天社

復路は九十九参道へ
鞍馬の夕暮れ 鳥のさえずり

㉑中門
静かで厳かな門をくぐる

⑰義経公供養塔
牛若丸が7歳から10年過ごした
東光坊の跡地に建立されたという
花が供えられていた🌹

⑯川上地蔵堂
牛若丸の守り本尊
修行のとき参拝したと言われる

⑭由岐神社
鞍馬の火祭は日本三大火祭のひとつ
古くより安産・子宝の神様として信仰あり

拝殿がすごく素敵だ
桃山時代の代表的な建築物で
国の重要文化財とのこと

御神木「大杉さん」
樹齢800年
願いが叶うとされている

またゆっくりお参りしたい

⑫魔王の瀧
ラストに凄いところに来た
瀧は今は流れていないようだ

瀧の下あたりに魔王之碑

無事に仁王門に到着

鞍馬山の思い出に
義経のてぬぐいを購入
歌が添えられていた
おん母の ぬくもりほどに 及ばねど
安らぎ給え 老杉のもと
(信樂 香仁)
牛若丸-源義経の御魂は
なつかしい鞍馬山に戻り、
遮那王尊として安らいでいる
義経と義経を愛する人々に思いを馳せた
京都の初夏の里山あるきに感謝




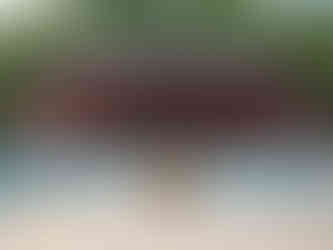



コメント